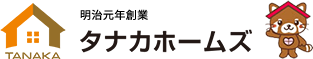Blog
スタッフブログ
2025年2月11日 / 家づくり
【今注目!】団地リノベーション!団地とは何かや分譲公団住宅を賢く使うためのヒントを解説

マンションや一戸建てが一般的な現代で「団地」という選択肢に迷いがある方も多いのではないでしょうか。
とくに近年注目を集めている団地リノベーションについて、具体的な費用や注意点が知りたいという声も増えています。
本記事では、
• 団地の基礎知識
• 人気の分譲公団住宅の特徴
• リノベーションのポイント
など、これから団地での暮らしを検討される方に役立つ情報を詳しく解説します。
ぜひ最後までお読みください。
目次
1.そもそも団地とは何か?
団地とは、複数の共同住宅が計画的に建てられた住宅地のことです。
現在のUR都市機構の前身である日本住宅公団が1955年に設立され、供給開始したことで全国に広がりました。
典型的な団地では、似たような中高層の建物が並び、集会所やスーパーマーケットなどの生活施設も整備されています。
住民同士のコミュニティ形成にも配慮した設計となっており、日本の都市部における代表的な住まい方のひとつとなっています。
2.団地にはいくつかの種類がある
団地は大きく4種類に分類されます。
• 公営住宅
• UR賃貸住宅
• 公社住宅
• 分譲公団住宅
運営主体や入居条件が異なり、それぞれ特色があります。以下で詳しく解説します。
公営住宅
都道府県や市区町村が運営する低価格の賃貸住宅です。
家賃は民間の半額程度に設定され、初期費用も抑えられます。周辺には公園や緑地が整備されており、良い住環境の物件が多いです。
ただし入居には収入制限があり、基準を超えると退去が必要となります。
UR賃貸住宅
UR賃貸住宅は、UR都市機構が運営する中堅所得者向けの賃貸住宅です。
仲介手数料・礼金・更新料が不要という特徴があります。入居には収入基準があり、家賃額に応じて異なります。UR賃貸住宅は長期的な居住を前提とした、安定した住まいとして評価が高いです。
また、高齢者や障がい者向けの特別な制度も用意されています。
公社住宅
公社住宅は、地方住宅供給公社が提供する賃貸住宅で、公営住宅よりも所得制限が緩やかです。
他の団地と同様に礼金や仲介手数料が不要で、更新料も不要なため長期居住に適しています。多様な住宅タイプと立地を用意しており、若年世帯や子育て世帯向けの割引制度など、多様な世帯に対応した制度も整備されています。
ただし、公社住宅の家賃は収入に応じて変動することはなく、周辺の民間賃貸住宅と同水準の設定が多いです。
分譲公団住宅
分譲住宅は、購入して所有する集合住宅です。
1960年代以降、都市部を中心に供給が始まり、当時最新の設備を備えたモダンな住まいとして人気を集めました。学校や郵便局なども設置された大規模な団地も多く、便利な生活環境が整っています。ローン返済後は管理費のみとなり、経済的なメリットも魅力のひとつとなっています。
3.分譲公団住宅のメリット
現在「中古住宅」として販売されている団地は、かつて分譲されていた公団住宅です。
その魅力を紹介します。
物件価格がリーズナブル
公団住宅は、同エリア・同等築年数の中古マンションなどに比べ、分譲価格がリーズナブルです。
物件の購入価格が抑えられるため、リノベーションに費用を回せます。自分の思い通りのアレンジが楽しみやすいでしょう。
住環境がよい
公団住宅は、広い敷地にゆったりと建てられていることが多く、圧迫感がありません。
棟と棟との間が公園や庭になっていることも多くあります。団地の周りには、商店街やスーパー、病院なども充実しています。
管理体制が整っている
URが運営しているため、管理も行き届いています。建物や敷地内は業者によって整備され、常時、緑や花であふれる豊かな空間を楽しめます。
古い建物でも、民間に比べて耐震診断・改修が進んでいることがほとんどです。
アクセスがよい
交通アクセスは、利用者数が見込めるところほど整備が進みます。
団地には多くの人が住んでいるため、近くに駅があったり、複数のバス路線が乗り入れていたりします。保育園や小学校も、徒歩圏内にあるでしょう。
4.分譲公団住宅のデメリット
分譲公団住宅には、いくつかのデメリットもあります。しっかりと理解したうえで、購入を検討しましょう。
築年数の古い物件が多い
現在流通している分譲公団住宅の大半は、古い物件です。水道管など設備面や、音漏れなどのトラブルが起こりやすいでしょう。
また、昭和40年頃までに建設された団地では、5階建てでもエレベーターがないおそれもあります。
マンションとサイズ感が異なる
団地では、「団地間」と呼ばれる通常よりも小さな畳が使われていることがあります。マンションとはサイズ感が異なる可能性もあるのです。
また、小型エレベーターしかなければ、大きい荷物の搬入も困難かもしれません。
自治会・近所付き合いが必要になる
団地には、自治会・自治体が設置されていることも多いようです。自治会によって細かいルールが定められていることも想定されます。
煩わしいと感じるかもしれませんが、不測の事態に助け合えるコミュニティが形成されていると捉えることもできます。
室内工事に制限がある
多くの団地は、コンクリート壁構造です。堅牢な部屋が安価で手に入るのはうれしい反面、どうしても壊せない壁があれば、室内工事に制限が生じます。
給湯器やエアコンを取り付ける際には、配管スペースや天井高などにも注意が必要です。
5.いま団地リノベーションが注目を集めている
今、団地の価値を見直して再生する動きが広まっています。ここでは、団地再生の取り組みを解説します。
団地の「新しい価値づくり」
団地は今、地域のコアエリアとして注目され始めています。
公園があり、周辺施設の充実によって生活利便性の高い環境は、子育て世代にとってもメリットが多いはずです。
若い世代に住んでもらうための取り組みも進んでいます。そのひとつが、リノベーション・DIYです。
分譲団地の「団地リノベーション」
3DKから2LDKにするなど、古い団地を時代に合った間取りに変更したり、最新の設備に置き換えたりと、よい住環境は残しつつ、入居者個々の生活満足度を高められるのが団地リノベーションです。
耐震工事やエレベーターの設置など、建物全体のリノベーションを実施して若い世代を誘致する団地も増えています。
賃貸団地の「DIY住宅」
賃貸団地の一部でも、入居者による自由な模様替えや一定のリフォームを認める「DIY住宅」が登場しています。
通常の賃貸住宅で求められる原状回復義務が免除されるのが特長で、なかには、工事期間の賃料が無料になるところもあります。
6.分譲団地リノベーションで押さえておきたいポイント
分譲団地のリノベーションを実施する際には、どのような点をおさえておけばよいのでしょうか。
ここからは団地リノベーションをする際に抑えておきたい4つのポイントについて解説します。
工期と費用
分譲団地のリノベーションにおける工期は、一般的に1~5か月程度が目安となります。
設備や内装を全面的に改修するフルリノベーションの場合、およそ600万円から1,800万円ほどの予算が必要です。基礎部分の修復や高級設備の採用は費用を大きく左右します。
また、給排水管の取り替えや断熱工事など、見た目には現れにくい部分にも相応の費用がかかります。
工事の優先順位を明確にし、予算配分を慎重に検討しましょう。 資金計画では、予備費として総額の1割程度を確保しておくと安心です。工事中の仮住まい費用も忘れずに計上する必要があります。
団地リノベーションの制約
分譲団地は、柱の代わりに壁で建物を支える壁式構造が一般的です。建物の安全性を支える耐力壁と呼ばれる壁は取り壊しができないため、間取りの変更には制限があります。
特に築年数が古い物件ほどコンクリート壁が多く、天井も低めです。
また給排水管の位置も自由に変更はできず、キッチンやお風呂などの水回り設備の移動には大きな制約があります。 このような構造上の特徴を理解したうえで、実現可能な間取り計画を立てることが重要です。
制約を逆手にとり、既存の構造を活かした魅力的な空間づくりを目指しましょう。
断熱性能の問題
古い建物が多い団地では、断熱材が十分に入っていないケースがみられます。
そのため現代の住宅と比べると冬場は寒く、夏場は暑いです。冬場は、窓からの隙間風や部屋の温度差から生じる結露に悩まされる可能性があります。
快適な室内環境を実現するには、窓の断熱改修や床暖房の設置などの対策が有効的です。 断熱性能自体をあげると、冷暖房費の削減にもつながり、長期的な視点では投資効果も期待できます。
しかしコストがかかり、施工の難易度も高いです。
工事の際は、結露対策も含めた専門家との十分な相談が必要でしょう。 施工方法によって効果や費用が大きく異なるため、複数の提案を比較検討しましょう。
優先順位
リノベーションの成功には、適切な優先順位付けが不可欠です。
最優先は配管の劣化確認と水回り設備の整備です。水漏れは建物全体に深刻な影響を及ぼすため、老朽化した配管の交換はした方が良いでしょう。
次に断熱性や防音性といった基本性能の向上を検討します。
その後に和室の洋室化や収納スペースの拡充など、生活様式に合わせた改修を進めていきます。
内装や設備の グレードアップは最後に検討し、予算の状況に応じて取捨選択すると良いでしょう。 計画的な工事の進め方が、快適な住まいづくりの鍵となります。
7.公団住宅を相続したときに知っておきたいこと
親や親戚などから、公団住宅を相続するケースもあるでしょう。その際に知っておくとよいことを解説します。
相続にかかる税金
不動産の相続で生じる税金は、2種類あります。このうち、必ず支払うのは、登録免許税です。
不動産を相続したら名義を変更(相続登記)しなければなりませんが、その際に「固定資産税評価額 × 0.4%」が課税されます。 もう1つは相続税です。
こちらは、必ず発生するものではありません。相続財産の合計額が基礎控除額(3000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合にのみ支払います。
相続後の方向性
不動産相続後の方向性は、主に3つあります。
最もシンプルなのは、そのまま自分が住む方法で、費用をかけずに住まいが手に入ります。
住まない場合には、売却や賃貸で収益化しましょう。購入・入居希望者を集めるには、リフォームを実施してから売ったり貸したりするのがおすすめです。
8.公団住宅相続後に起こる注意点
相続しても住まず、売却も賃貸もしない場合は、空き家になります。空き家のままで置いておくのは、あまりおすすめできません。
維持コストがかかる
不動産は、「所有しているだけ」でも維持コストがかかります。
月ごとでは管理費や修繕積立金、年単位では固定資産税や火災保険料などの支払いが発生するうえ、水道や電気を維持していれば、使わなくても基本料金がかかります。
空き家による劣化に注意する
住宅は、定期的に手入れをしないと想像以上のスピードで劣化するといわれています。
自分で管理できないときには空き家管理を請け負う業者に委託する手もありますが、費用や連絡を取る手間が生じます。
9.公団住宅の売却で直面する問題
公団住宅を売却しようと思ったら、いくつかの問題に直面するでしょう。
どのようなことが想定されるのでしょうか。
団地の売却は困難
土地の所有がない団地は、敷地所有権つき物件より売却価格が安くなる可能性が高いでしょう。
多くの団地は築年数も古いため、売却自体も困難だと予想されます。状態次第では、購入者からリフォームや修繕が求められることもあります。
仲介売却と買取の選択が必要
不動産の売却方法には、不動産会社に買主を探してもらう仲介と、不動産会社が買主となって直接買い取ってもらう買取があります。
仲介は、相場価格で売却できる可能性がありますが、売れるまでに時間がかかりがちです。
また、販売活動も必要でしょう。買取は、確実に、迅速に現金化できる一方、売却価格が相場より低くなりやすいのがネックです。
公団住宅売却の税金が必要
団地を売却した金額が、「不動産取得額+売却にかかった経費(譲渡費用)」を上回れば、「利益(譲渡所得)が出た」ということで所得税の課税対象になります。
反対にマイナスになってしまうなら、確定申告は不要です。
10.まとめ
分譲公団住宅は、価格の手頃さや住環境の良さが魅力。リノベーションで快適な住まいにできますが、構造の制約や断熱性能には注意が必要です。
お手頃な価格で理想の住まいを探している方には、タナカホームズの規格住宅もおすすめ。
気になる方は、お気軽にお問い合わせください
会社名:田中建設株式会社
部署名:経営企画部
執筆者名:大勢待 昌也
執筆者の略歴 保有資格 住宅ローンアドバイザー
執筆者のSNSのリンク:https://www.facebook.com/oosemachi
最近の投稿